大学受験対策いつから始める?学年・時期別の勉強のポイント
大学受験勉強を始める時期は早ければ早い方が有利です。ただ、始めるのが遅いからといって志望校合格をあきらめるのはまだ早いです。また、時期によって最適な勉強方法は変わります。高1~高3冬まで、時期に応じた大学受験対策のポイントをご紹介します。
近畿大学入試科目別対策

引用元:近畿大学公式ホームページ
※調査概要:2025/6/13–7/18、インターネット調査、対象=大学受験で子供が教育サービスを利用した保護者 n=475。表示比率は「安い・やや安い・妥当」合計。
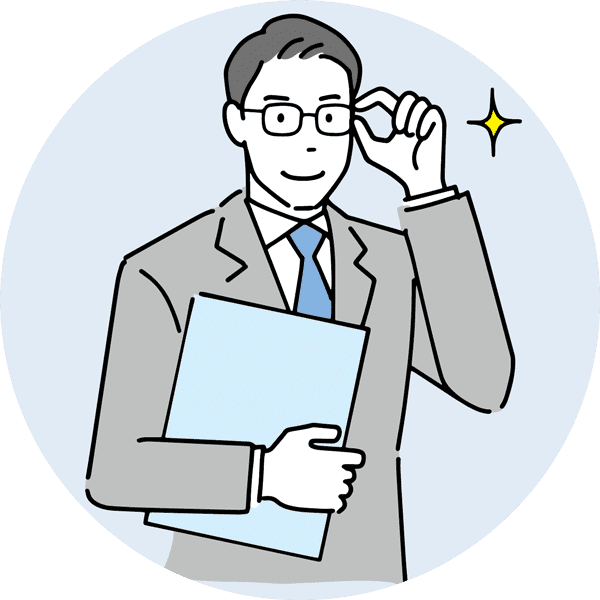
近畿大学の科目別の入試傾向をもとにした各科目の勉強法や対策のポイント
近畿大学合格を目指す方向けに、各入試科目の入試傾向から各科目の勉強法と対策のポイントをより詳細に解説。近畿大学対策のオーダーメイドカリキュラムの詳細についても案内しています。
近畿大学の英語入試では、読解問題が中心となっています。
長文読解では、内容理解を問う設問が多く、文脈からの推測力や要旨把握能力が試されます。
また、文法・語彙問題も出題され、基本的な文法知識や語彙力が求められます。
読解力の向上:日頃から英字新聞や英語のニュース記事を読む習慣をつけ、速読力と内容把握力を鍛えましょう。
文法・語彙の強化:基本的な文法事項を再確認し、頻出単語や熟語を効率的に覚えることで、文法・語彙問題への対応力を高めます。
過去問演習:近畿大学の過去問を解くことで、出題傾向を把握し、時間配分の感覚を養います。
リスニング対策:リスニング問題が出題される場合に備え、英語の音声教材を活用して、聞き取り能力を向上させましょう。
英作文の練習:自由英作文が課される場合もあるため、日頃から英語で自分の意見をまとめる練習を行い、表現力を高めます。
これらの対策をバランスよく進めることで、近畿大学の英語入試に対応できる実力を養成しましょう。
近畿大学の数学では、数学I・A・II・Bを中心に、標準レベルからやや応用レベルまで幅広く出題されます。
特に微分積分、図形と方程式、数列、確率などが頻出単元で、思考力と計算力の両方が問われます。
選択問題と記述式問題がバランスよく配置されており、限られた時間で正確な処理が求められます。
頻出分野の重点対策:過去問を分析すると、数列・微積・確率の出題率が高いため、まずはこれらの単元をしっかり固めましょう。典型問題の解法をパターン化して覚えることが重要です。
計算力の強化:難問に時間を割くためにも、標準問題は正確かつスピーディに解けるようにしておきましょう。計算ミスを減らすために毎日計算トレーニングを積むことが効果的です。
過去問演習の活用:過去5〜10年分の問題を通して出題傾向を掴むとともに、時間配分の感覚を養いましょう。問題傾向に慣れることで、本番でも落ち着いて対応できます。
応用問題への挑戦:標準問題だけでなく、やや難の応用問題にも取り組み、解法の引き出しを増やすことで対応力が身につきます。
限られた時間の中で、頻出単元を重点的に攻略し、過去問で実戦力を高めることが合格への鍵となります。
近畿大学の国語は、現代文2題と古文1題で構成されるのが一般的です。
現代文は評論文や随筆が中心で、文章の論理構造を正確に把握する読解力が求められます。設問形式は記号選択が多く、文章全体の要旨把握や文脈判断に重点が置かれています。
古文は語彙・文法の知識を前提とした読解問題が中心で、古典常識の理解も問われます。
現代文対策:評論文や随筆文の読解演習を通して、論理的に読み解く力を鍛えましょう。設問ごとに根拠を意識しながら解く練習が有効です。
語彙・文法の基礎固め:古文単語帳や文法書を活用し、頻出語や文法事項を確実に身につけましょう。特に助動詞や敬語の識別が得点に直結します。
古文読解の訓練:主語の補足や係り結び、和歌の挿入など、古文特有の表現に慣れておくことが重要です。音読も効果的な手段です。
過去問で実戦力アップ:近畿大学の過去問を繰り返し解き、出題形式や難易度に慣れることで本番への対応力を高めましょう。
バランスよく現代文・古文に取り組み、基礎力と応用力の両方を養うことが合格への近道です。
近畿大学の物理では、力学・電磁気・熱力学・波動といった基本的な分野から幅広く出題されます。全体的に標準〜やや応用レベルの問題構成で、計算問題が中心です。図やグラフを読み取る力や、現象を数式で表現する理解力が問われる傾向があります。また、選択肢だけでなく記述式も含まれ、思考過程まで問われる問題も見られます。
・基本公式の理解と運用
物理は公式の暗記だけでなく、意味や成り立ちを理解し、様々な状況に応用できる力が求められます。教科書レベルの問題を繰り返して、基礎を盤石にしましょう。
・計算力を鍛える
単位や桁数、ベクトルの取り扱いなど、正確な計算が重要です。複雑な計算でも焦らず対応できるよう、日常的に手を動かして練習しましょう。
・図解とイメージトレーニング
物理現象は視覚的に捉えることが理解のカギになります。問題を図に書いて整理するクセをつけ、イメージと数式を結びつける習慣を意識しましょう。
・過去問を使った演習
出題形式に慣れるために過去問を活用し、頻出分野や解法の傾向を掴んでおきましょう。自分の苦手分野も客観的に把握できます。
基礎を固めつつ、典型問題を通じて応用力を養うことが、合格への近道となります。
近畿大学の化学では、理論化学・無機化学・有機化学の3分野からバランスよく出題されます。特に理論化学に重点があり、化学反応式の理解や計算問題が多く見られます。記述量は標準的で、基本からやや応用レベルまで幅広い問題が出題されます。知識だけでなく、思考力・計算力も求められる構成です。
・理論化学の徹底理解
モル計算、化学反応、気体の法則などは頻出です。公式を丸暗記するのではなく、なぜその式になるのかを理解しながら演習を積みましょう。
・暗記に頼らない無機化学対策
色・沈殿・気体の性質などをただ覚えるのではなく、周期表や反応の法則性と合わせて理解することが効率的です。
・有機化学は構造と反応をセットで覚える
構造決定問題や反応の流れを理解することで、応用問題にも対応しやすくなります。名称や官能基の特徴を整理しながら覚えましょう。
・過去問で出題傾向を掴む
近畿大学の過去問を複数年分こなすことで、分野ごとの出題頻度や形式を把握し、得点源にできる分野を見極めましょう。
基本事項を深く理解し、演習を通じて定着させることが合格への最短ルートです。
近畿大学の生物は、大問4題構成で全問マーク式。文章の正誤判断や用語の組み合わせ選択など、細かな知識を問う問題が多く見られます。頻出分野は「生命現象と物質」「生殖と発生」「環境応答(動物・植物)」「体内環境の維持(免疫含む)」など。DNA、呼吸、光合成、遺伝計算、植物ホルモン、組織培養といった基礎事項は必須。選択肢が多く、正確な知識の整理が求められます。
出題は標準レベル中心で、教科書や基礎問題集をマスターしていれば十分対応可能です。とはいえ、遺伝や実験考察などで難易度の高い問題も一部含まれるため、得点できる問題を見極めて対応することが重要です。配点は100点満点で、学部ごとの配点比率には差があります。
教科書の例題・基本問題を徹底的に繰り返し、基礎力の定着を図りましょう。例年似た出題傾向があるため、過去問演習が有効です。頻出分野を重点的に対策しながら、語句・用語の曖昧さをなくし、マーク式に対応できる精度の高い学習を意識しましょう。
1科目60分で大問4題・約50問の出題。1問にかけられる時間は限られるため、スピード感を持った演習が不可欠です。迷った問題に時間をかけすぎず、確実に得点できる問題から解くトレーニングをしておきましょう。
近畿大学の日本史は、全問マーク式で記述問題はありません。大問4題・小問約40問が出題され、試験時間は60分。原始〜現代まで幅広い時代から、政治・経済・外交・文化など多様な分野の問題が出題されます。史料問題が1〜2題含まれ、写真や地図を活用した設問も特徴です。年号や数字を問う問題もあり、知識の正確さが問われます。
出題レベルは教科書の基礎〜標準。教科書ベースの知識を正確に理解していれば対応可能です。1問あたり2〜3点の配点と考えられ、合格には高得点が求められます。特に文系学部では7割前後が合格ラインとなるため、取りこぼしのない確実な解答力が求められます。
まずは教科書を軸に、基本用語や人物、重要事項を確実に覚えましょう。時代の流れだけでなく、分野間の横のつながりを意識した学習が効果的です。史料問題対策として、史料集に目を通し形式に慣れることも重要です。過去問や問題集を活用し、時間配分を意識した演習を行いましょう。
近畿大学の世界史は全問マーク式で、大問2題・小問約40問構成、試験時間は60分です。欧米史1題、アジア・アフリカ史1題と、出題範囲は幅広く、空所補充・正誤組み合わせ・配列問題・年表・地図を使った問題など多様な形式が含まれます。特定の地域に偏らず、満遍なく対策することが求められます。
出題は教科書レベル中心で、奇問・難問は出題されません。1問あたり2〜3点換算とされ、9割得点を目指すならミスは4問以内に抑える必要があります。教科書の内容を確実に暗記し、用語や年号、地理的知識も含めて正確に覚えておきましょう。
出題分野は政治史中心ですが、文化史・年号・地理も出題されるため、教科書の全範囲を網羅的に学習することが大切です。各地域の歴史的流れだけでなく、文化・経済との関連も整理しましょう。年号や期間は出来事と関連付けて覚え、地図帳を使って地理的背景も理解しておくと得点力が上がります。
全問マーク式とはいえ、40問を60分で解く必要があるため、1問1分ペースが目安です。配列問題や地図問題で時間を取られないよう、日頃からスピードを意識した演習を積んでおきましょう。
近畿大学の地理は、全問マーク式で大問3題・小問40問程度が出題され、試験時間は60分です。地図・地形図・グラフなどの資料を使った問題が中心で、視覚資料の読み取り力が問われます。出題内容は、自然地理・人口・産業・貿易・政治など多岐にわたり、国や地域の特徴を問う設問も頻出です。
出題は教科書レベルが中心で、奇問や難問はほとんどありません。1問あたりの配点は2~3点と想定され、高得点を目指すにはケアレスミスの防止が必須です。9割得点を狙う場合、ミスは4問以内に抑えたいところです。
基本用語の理解に加え、資料集を使った学習が効果的です。写真・地図・統計資料に慣れておくことで、問題形式への対応力が高まります。「地形図」「地域特性」「産業・人口」などの頻出テーマは重点的に対策しましょう。また、参考書は絞って繰り返す学習が得点力を高めます。
試験時間60分で40問前後を解くため、1問1分のペースで進める意識が必要です。スムーズに解ける問題から取り組み、資料読解に時間がかかる設問は後回しにする判断力も大切です。
近畿大学の政治・経済は、全問マーク式で小問約40問、試験時間は60分です。空所補充、下線部に関連する設問、正誤選択、出来事の発生年の配列問題など、多様な設問形式が特徴です。出題分野は、財政・金融、経済主体、通貨、日本経済の歴史と現状などが中心です。
出題レベルは標準的で、教科書や資料集の範囲からの出題が基本です。ただし、細かな知識を問う問題も含まれており、確実な理解が求められます。1問2〜3点換算とされ、高得点を目指すには4問以内のミスに抑えることが理想です。
まずは教科書・資料集を中心に、基礎知識の理解を固めましょう。図表や年表、統計データにも目を通し、時代の流れや経済構造の変遷をおさえることが重要です。正誤判定問題が多いため、用語の意味や文脈での使われ方を理解しながら学習を進めましょう。時事問題にも対応できるよう、公務員試験対策本などでの補強も有効です。
60分で40問を解く必要があるため、1問1分を意識したスピーディな解答が求められます。即答できる問題を優先し、時間がかかりそうな問題は後回しにするなど、時間管理のトレーニングを行いましょう。
近畿大学の学部別の受験対策はこちらです。
2026年度(令和8年度)入試で近畿大学合格を目指す受験生のあなたへ。
ただがむしゃらに勉強をしても近畿大学に合格することはできません。近畿大学に合格するためには、近畿大学のそれぞれの入試科目のポイントを押さえた勉強をする必要があります。
じゅけラボでは、以下の3つのポイントに着目して、近畿大学の2026年度(令和8年度)入試を受験する方が合格する為に必要な、偏差値偏差値55~60のレベルに達するための受験対策カリキュラム・学習計画を提供しています。
実は、多くの受験生が現状の自分の学力レベルを把握できておらず、自分の学力レベルより高いレベルや赤本などの過去問から受験勉強を始める傾向にあります。参考書や解説集、演習問題の選び方でもそうです。近畿大学の受験では中学~高校の基礎固めが重要です。近畿大学に合格する方法とは、テクニックではなく、自身の実力に適切なレベルから順に近畿大学に合格するために必要な学習内容を、正しい勉強法で効率よくスピーディーに進めることが必要です。
じゅけラボでは、近畿大学の入試問題はどんな傾向があり、どんな対策が必要なのかを考慮したカリキュラム・学習計画に加え、効率よく受験勉強を進めるための勉強方法を用意しています。まずは学力テストであなたの現状の学力レベルを把握してレベルに合ったカリキュラムを作成し、近畿大学の2026年度入試に合格するために必要な学習計画と正しい勉強方法を提供します。
また、じゅけラボのカリキュラムは、塾や予備校に通っている生徒でも塾や予備校の勉強の邪魔をすることなく取り組むことが可能です。また、正しい勉強方法が具体的に示してあるので、塾なしで家で勉強する場合にも最適です。
「近畿大学に合格できる」
あなただけの学習プランをご用意します。
大学受験に必要な全科目を受講できて
1ヶ月16,280円(税込)
模試の結果が悪かった、E判定だったことで「近畿大学に受かる気がしない」とやる気をなくしてしまっている受験生のあなた、あきらめるのはまだ早いです。
じゅけラボでは、現状の学力から近畿大学に合格するための最短のカリキュラムを提供します。また、「高3の8月から勉強を始める場合」「高3の9月から勉強を始める場合」など、始めた時期によってカリキュラムのスピードや量を調整することも可能です。
近畿大学を目指す受験生から、「夏休みや8月、9月から勉強に本気で取り組んだら近畿大学に合格できますか?「10月、11月、12月の模試で近畿大学がE判定だけど間に合いますか?」という相談を受けることがあります。
勉強を始める時期が10月以降になると、現状の偏差値や学力からあまりにもかけ離れた大学を志望する場合は難しい場合もありますが、対応が可能な場合もございますので、まずはご相談ください。
近畿大学に受かるには必勝の勉強法が必要です。仮に受験直前の10月、11月、12月でE判定が出ても、近畿大学に合格するために必要な学習カリキュラムを最短のスケジュールで作成し、近畿大学合格に向けて全力でサポートします。
近畿大学に「合格したい」「受かる方法が知りたい」という気持ちがあるあなた!合格を目指すなら今すぐ行動です!
合格発表で最高の結果をつかみ取りましょう!
大学受験勉強を始める時期は早ければ早い方が有利です。ただ、始めるのが遅いからといって志望校合格をあきらめるのはまだ早いです。また、時期によって最適な勉強方法は変わります。高1~高3冬まで、時期に応じた大学受験対策のポイントをご紹介します。
現在全日制高校に在籍中の不登校の高校生、通信制高校、定時制高校の方で、近畿大学に行きたいのに、現在の自分の学力に対する自信のなさから「自分には無理だ」と思い込んで、最初から近畿大学受験にチャレンジして志望校へ進学する事を諦めていませんか?
高校卒業、通信制高校卒業、または高卒認定試験に合格していれば近畿大学受験をする事が出来ます。
あと必要なのは単純に学力・偏差値です。近畿大学に照準を合わせた大学受験戦略を立てて、受験に必要な科目の最低合格点をクリアできる学力を目指す最適な勉強法に取り組む事で、近畿大学合格も十分に可能性があります。
現役高校生の受験生だけでなく、現在浪人生、または社会人の方で近畿大学受験を目指している方に、近畿大学合格に向けたオーダーメイドの受験対策カリキュラムを作成致します。
今の学力から近畿大学合格に必要な学力レベルになる為の学習内容、学習量から逆算して使用教材(参考書・問題集)と学習ルートを確定して学習計画に落とし込んでいきます。
しかも、じゅけラボ予備校は近畿大学入試に必要な全ての科目を学べて1ヶ月16,280〜18,480円(税込)の低価格の月謝で受講出来ますので、浪人生や社会人の方にとって経済的に続けやすい安心の料金体系です。
近畿大学合格を目指す浪人生、社会人の方は是非一度お問い合わせください。
今の偏差値から近畿大学の入試で確実に合格最低点以上を取る為には、入試傾向と対策を知って受験勉強に取り組む必要があります。
近畿大学には様々な入試制度があります。自分に合った入試制度・学内併願制度を見つけて、受験勉強に取り組んでください
近畿大学に合格する為の勉強法としてまず最初に必要な事は、現在の自分の学力・偏差値を正しく把握する事。そして次に近畿大学の入試科目、入試傾向、必要な学力・偏差値を把握し、近畿大学に合格できる学力を確実に身につける為の自分に合った正しい勉強法が必要です。
答えは「今からです!」近畿大学受験対策は早ければ早いほど合格する可能性は高まります。じゅけラボ予備校は、あなたの今の実力から近畿大学合格の為に必要な学習内容、学習量、勉強法、学習計画のオーダーメイドのカリキュラを組みます。受験勉強はいつしようかと迷った今がスタートに最適な時期です。
高1から近畿大学へ向けた受験勉強を始めれば合格率はかなり高くなります。高1から近畿大学受験勉強を始める場合、中学から高校1年生の英語、国語、数学の抜けをなくし、特に高1英語を整理して完璧に仕上げることが大切です。高1から受験勉強して、近畿大学に合格するための学習計画と勉強法を提供させていただきます。
可能性は十分にあります。夏休みを活用できるのは大きいです。現在の偏差値から近畿大学合格を勝ち取る為に、「何を」「どれくらい」「どの様」に勉強すれば良いのか、1人1人に合わせたオーダメイドのカリキュラムを組ませて頂きます。まずは一度ご相談のお問い合わせお待ちしております。
可能性は十分にありますが、まず現状の学力・偏差値を確認させてください。その上で、現在の偏差値から近畿大学に合格出来る学力を身につける為の、学習内容、勉強量、勉強法、学習計画をご提示させて頂きます。宜しければ一度ご相談のお問い合わせお待ちしております。
現状の学力・偏差値を確認させて下さい。場合によりあまりにも今の学力が近畿大学受験に必要なレベルから大きくかけ離れている場合はお断りさせて頂いておりますが、可能性は十分にあります。まずはとにかくすぐにご連絡下さい。現在の状況から近畿大学合格に向けてどのように勉強を進めていくのかご相談に乗ります。
あなたの学力
×
志望大学の傾向・難易度に合わせた
近畿大学専門の
受験対策
国公立大学
私立大学
国公立大学
国公立大学
国公立大学
「志望大学に合格できる」学習プランを提供